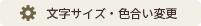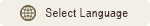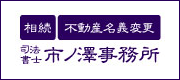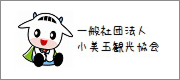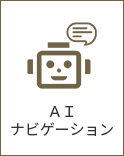定例記者会見(令和7年8月29日)
会見概要
【日時】
令和7年8月29日(金曜日)10時00分~
【場所】
小美玉市役所本庁舎2階第2・第3会議室
【出席者】
参加報道機関:茨城新聞社、茨城放送、共同通信、建設未来通信社、、日本工業経済新聞社、読売新聞
市:市長、副市長、教育長、市長公室長、秘書課長、各部署担当
【記録】
秘書課
説明案件
質疑応答の要旨
(1)議案等に関する質疑
- 議案:小美玉市運動広場条例の一部を改正する条例について
記者:
堅倉運動広場が廃止されるということですが、これまでどのような活用がされてきたのか、利用者数はどれくらいいたのか、また、廃止後の跡地について計画が決まっているのか、といった点を教えてください。
担当:
堅倉運動広場につきましては、これまで市内の団体及び事業者が利用しており、主に少年野球やソフトボール等に使われていました。令和5年は222人の利用となっており、近年利用が減っているということで廃止をさせていただきます。
またこの土地は借地ですので、廃止後は施設を解体し、地権者の方に返却をいたします。
- 補正:コミュニティ活動促進費(地域活性化起業人制度による派遣受入)
記者:
臺灣新聞社(たいわんしんぶんしゃ)から、地域活性化企業人制度を活用して社員の派遣を受け入れるということですが、当社はどういった企業なのでしょうか。
また、業務内容として、友好交流都市等との交流事業や、SNSを活用した情報発信とありますが、もう少し具体的に教えてください。
市長:
臺灣新聞社は、本市の友好交流都市となっている台湾の新北市淡水区に支社があり、台湾に関するマーケティングや広報に関する専門の知識を有しています。
新北市淡水区と友好交流覚書を締結し、交流事業を積極的に進める中で、同社より台湾との交流推進と地域発展への協力についてご提案をいただき、7月に包括連携協定を締結したところです。
本市の魅力発信や臺灣新聞社のネットワークを最大限に活かした国際交流を推進していただくとともに、新たな風として地域に活力を吹き込んでいただきたいと考えています。また、あわせて市職員の国際交流に関する意識の向上につながることも期待しております。
台湾では小学生のころから英語教育に力を入れているということで、特に英語を中心とした子どもたちの交流をしたいと考えています。すでに一度台湾の子どもたちが、本市の学校に来て交流を行っており、今後は、本市の子どもたちを台湾新北市へ派遣したいと考えています。姉妹都市であるアビリンのあるアメリカの場合は時差があり難しいですが、台湾は時差がないので、リモートでの子供たちの交流も実施していきたいと考えています。
また、大人の交流として、様々な産業の関係も考え、訪問団を結成し2月に派遣をしたいと考えています。
本制度を活用し、臺灣新聞社から派遣いただいた方には、そういった際に台湾との中継の役目も担っていただきたいと考えています。
副市長:
ただいま市長からの説明があった通りですが、より具体的には、新北市淡水区との連絡調整、例えば文書の翻訳や連絡・手紙のやりとり等、また、視察等の際のアテンドや通訳等を考えています。
派遣される方は、台湾の大学を出て、英語も堪能で、日本にも語学留学で1年ほど来ているということで、母国語の中国語・英語・日本語と、3ヶ国語に通じているということで、色々とアシストにしていただく予定です。
また、臺灣新聞社は、淡水区に支社があり、本社は豊島区池袋にあります。新聞も発行していますがネットでの発信を中心に行っているということで、小美玉市の魅力をSNSで広く台湾の方にも情報発信をお願いしようと考えています。
記者:
小美玉市では、海外からの人材を受け入れるのは初めてですか。
市長:
初めてです。
(2)その他市政全般に関する質疑
- 茨城空港の国際線制限撤廃について
記者:
茨城空港について、大井川知事が定例記者会見で、茨城空港の国際線発着に関する制限について大幅に緩和されたということを発表されました。市としても、これまで防衛省等へこの制限緩和について要望をされてきたと思いますが、改めて今回の決定について市長の見解を伺いたいと思います。
市長:
茨城空港は航空自衛隊との共用空港ということで今まで色々な制限がありました。
まず、国際線の出発や到着・駐機時間等の制限。それから、曜日によって乗り入れができないという制限。これらについて緩和されたということで、これから国際便においては増便に非常に有効な制度の改正となっています。
主に県と国の調整でありますが、市も申し入れを行い緩和になったということで、例えば、10月には清州空港への韓国便が3便から4便に増便することが決定しています。また、引き続き台湾便も増便の申請をしていると聞いています。
国内の方も、決定ではありませんが、神戸・福岡便もかなり利用客が多いので増便の可能性があるということです。
規制前は、空港利用客は約80万人が最大といったところでしたが、規制緩和になり、さらに県でも今後の施設拡張が正式に決まっており、200万人以上の利用客を見込んでいるということです。
本市にとっても、交流人口の増加につながりますので、今回の規制緩和については県に対して感謝をしているところです。
記者:
交流人口の増加が期待されるということですが、それを見越して、空港がある地元の市としてはどのような政策を進める考えですか。
市長:
私が県議会にいた頃から、空港前のにぎわいづくりを提案していましたが、本市では新まちづくり構想を計画しており、茨城空港前に、にぎわいづくりの交流施設を考えています。
浜松の航空自衛隊基地に、エアーパークという防衛省直轄の大きな航空博物館があり、そういったイメージの施設です。また、アメリカで共同訓練に来たときに、地元の人たちと交流したり、災害時の避難所にもなる場所として考えています。
それから、空港付近には空の駅「そ・ら・ら」がありますが、空港と「そ・ら・ら」の距離が少しありまして、交流施設はちょうどその真ん中あたりの県の土地に計画しています。茨城空港、新交流施設、「そ・ら・ら」と動線が繋がりますので、一帯のにぎわいが創出できればと期待しています。
記者:
浜松基地の展示施設のようなものを、今後、防衛省等に要望していくということでしょうか。
市長:
現在、空港の脇にファントム2機が展示してありますが、ちょうど空港施設を拡張する場所となりますので、移転しなければなりません。それを交流施設に展示してもらう予定となっています。
それから、浜松のエアーパークには、子どもに人気のフライトシュミレーターがありますので、そういったものも設置して体験していただくよう考えています。
- 消防職員の懲戒処分について
記者:
今月5日に職員の処分が行われた市消防本部のパワハラの件について、再発防止に向けてどういったことに取り組まれていますか。
市長:
この件につきましては、市民の皆さんにご迷惑をおかけしたこと、深くお詫びを申し上げます。
再発防止につきまして、早期に全職員向けのハラスメント防止の研修を実施し、職員の意識向上を図っていきたいと考えています。今までもこういった研修は実施していますが、さらに突っ込んだ研修を考えています。
また、消防本部に、新しくハラスメントの対策検討組織を立ち上げ、今後必要な対策を実施していきたいと考えています。
記者:
小美玉市だけでなく、近隣の消防でも色々なトラブルや問題が明らかになっています。やはり、消防は限られた人数の中で、配属先も限られていて人間関係の難しさもあるかと思います。
小美玉市では、消防と一般行政部門の人事交流は実施していますか。
市長:
幹部職員について、現在、行政職が消防長を担っていますが、若い人の人事交流はありません。
どうしても消防職は縦の関係も強いところで、その中で時代にそぐわない教育指導が起こりやすいので、改めて再発防止という観点で、ハラスメントがないように対策検討組織を作っていきたいと考えています。
記者:
人事管理の面だけでなく、装備の面でも、石岡市もかすみがうら市もそうですが、単独の消防本部だと、例えば年に数回しか使わないような、高層の建物まで届くようなはしご車も、それぞれが用意しなくてはならない。
そういった、予算の面でも、広域の消防本部を設置したほうがによいのではという意見もあるようですが、そういったことについてはいかがですか。
市長:
本市も、合併前は旧小川町・美野里町・玉里村で広域消防を作っておりました。
もう10年程前に、笠間市や石岡市、茨城町、大洗町、といった近隣自治体でそういった話も出ていたようですが、立ち消えになっています。ただ、最近、またそういった意見交換をやろうという話はきています。
例えば、本市では、はしご車はありませんが、化学消防車がありまして、これはあまり他の消防では持っていない。逆に、石岡市にははしご車がありますので、そういったことを考えると、近隣との将来的な広域もあるのかなと私は考えています。
記者:
意見交換はどこの自治体との話になりますか。
担当:
国が示す消防広域化推進に伴い、まずは小美玉市近隣の石岡市、笠間市、大洗町、茨城町等と情報交換程度を行っているところです。
- 第2回おみたま花火大会について
記者:
今月4日に、横浜市で開かれた花火大会にて、花火を打ち上げている台船で火災が発生したというトラブルがありました。火災の原因は第三者委員会を設置して検証中となっています。
小美玉市の花火大会も同じように霞ヶ浦の台船から花火を打ち上げるということですが、このトラブルを受けて、改めて確認や対策をしたことは何かありましたか。
担当:
横浜市での台船火災を受けて、花火会社と台船の上での安全管理を確認しております。その中で、細かい花火が引火する危険性があるので、そこを抑えながら、発数を変えずに調整をしているところです。
記者:
湖で打ち上げるということで、何かあった場合に船での避難が課題になってくると思いますが、そのあたりについても確認されていますか。
担当:
今月27日に実施した実行委員会にて、花火大会の避難計画を作成し、避難経路を示しています。